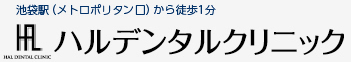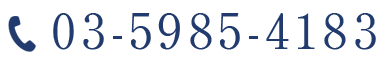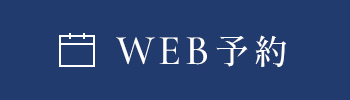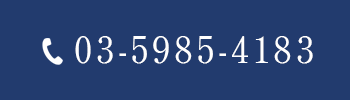健康寿命を伸ばすカギは“歯”!驚きの調査結果
こんにちは
春山です
毎年6月4日~10日は歯と口の健康週間。
老若男女問わず、歯と口の健康は全身の健康と密接な関係があります。
さまざまな研究で虫歯・歯周病の原因菌と全身疾患との関連性がわかってきています。
ここでは口腔状態の悪化が健康寿命に影響を及ぼす可能性を見ていきます。
年齢を重ねるとやがて高齢者になるので、シミュレーションしながら読み進めていてください。
健康寿命
日本人男女の健康寿命は下記のとおりです。
男性
平均寿命:81.05歳
健康寿命:72.57歳
平均寿命との差:8.48年
女性
平均寿命:87.14歳
健康寿命:75.45歳
平均寿命との差:11.69年
(いずれも令和4年)
参考:
健康寿命の令和4年値
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001363069.pdf
男女とも約10年健康ではない期間があります。
健康に暮らせなくなったら?
健康に暮らせない状態になった際私たちはどうなってしまうのでしょうか。
歯科・医科で考えると、糖尿病、脳血管疾患などの生活習慣病を患うことで健康的な生活を送れなくなるかもしれません。
その他、社会とのつながりが薄くなり社会的な孤立を経験する可能性もあるでしょう。
実は歯と関連のある健康寿命
実は歯・口腔の健康が健康寿命の長短に関係するという研究結果もあります。
たとえば北九州地域にある高齢者福祉施設の入居者を追跡調査した研究。
歯が1本もなく義歯をつけていない人の体の健康状態と心の健康状態が悪化するリスクは歯が20本以上残っている人と比較して下記のとおりでした。
体の健康状態:10.3倍
心の健康状態:3.1倍
その他にも全身の衰え(フレイル)なども口腔機能低下による影響の可能性があります。ただ、これに関しては義歯をつけるなど口腔機能を補うことで改善可能です。歯数・口腔機能の維持・メンテナンスに努めましょう。
見逃されがち…新しいお口の病気
比較的新しい歯科の病名に下記があります。
- 口腔機能発達不全症
- 口腔機能低下症
両方とも食べる・話すなどといった口の機能に関する病気です。前者は15歳未満の子ども、後者は50代以降の中高年層が主な対象となります。
ただ、知られていないことも多くあるのも確か。今回はこのうち口腔機能低下症の症状とその原因についてわかりやすく説明します。
50代未満の方についても知識として持っていただけると幸いです。
口腔機能低下症
口腔機能低下症は加齢などの要因で噛む・飲み込む・唾液分泌などの機能が低下。それに伴って食事・会話などに支障が出ている状態です。令和2年に口腔の新しい病気として認定されています。
以下の7項目のうち、3つ以上に当てはまったら口腔機能低下症と診断されます。
チェックしてみてください。
・口腔不潔
・口腔乾燥
・噛み合わせる力
・舌と口の運動機能
・舌圧
・噛み砕く力
・飲み込む力
原因
- 加齢
年齢を重ねるとどうしても口内の感覚や噛む・飲み込む・唾液分泌などの機能が低下します。
- 歯科疾患
虫歯・歯周病によって歯を失う、義歯が合っていないなどの理由で口内環境が悪くなることが原因です。
- 全身疾患
たとえば糖尿病や神経疾患などの全身疾患が口腔に影響を与えることがあります。
- 薬の副作用
服用している医薬品の副作用で唾液分泌量の低下や口腔乾燥を招きます。
- 口腔ケア
歯みがきしていない、定期検診を受けていないと口内が不潔になりやすく要注意です。
- 食生活・生活習慣
柔らかいものしか食べなくなるなどの偏った食生活、喫煙も関連があります。
これらのうち、どれかひとつではなく複数の要因が複合的に重なることが多いです。特に糖尿病は歯科疾患との関連性も指摘されています。今のうちから食習慣・生活習慣の見直しを図りましょう。
歯を失うと“脳”も老ける!?
日本の超高齢化社会で心配されるのが、口腔機能の低下です。JAGESプロジェクトの研究では、咀嚼機能の低下や歯の喪失が見られる人は3~9%程度主観的認知機能低下リスクの増加が見られました。
https://www.jages.net/project/industry-government/opera/?action=common_download_main&upload_id=11995
裏を返すと歯のケアをはじめとした口腔ケアをしっかり行えば認知機能の低下を防げる可能性があるということです。ここでは今のうちからできるケアについて書いていきます。
歯の治療・定期検診でケア
歯のグラつきや痛みなどの自覚症状があれば、早急に治療をしましょう。歯科疾患が自然治癒することはないので、早期発見・早期治療が王道です。自覚症状がなくても、定期的に通院して歯石除去や磨き残しのチェックなどを受けてください。
歯がなくなるとどうなる?
歯が少ないと、下記のようなことが起こり得ます。
-
咀嚼・嚥下機能の低下
歯が少ないと食べ物を噛み砕けなくなる他、飲み込みにも不便が出ます。
-
唾液分泌量の低下
歯が失われて影響が出やすいのが、噛む回数の減少です。
噛む回数が減ると、唾液の分泌量が減る可能性があります。
-
歯周病・虫歯の悪化
歯が欠損することで歯周組織の炎症悪化や口内が汚れやすくなる、歯周病菌や虫歯原因菌の繁殖につながります。
-
全身疾患への影響
栄養不足や筋力低下、感染症のリスクなど多方面へ影響を及ぼす可能性があります。
お口の機能維持のためにできること
-
義歯を入れる
歯を失った部分は、部分義歯やブリッジ、インプラントで補いましょう。
口に馴染むように調整することで噛む能力を取り戻すとともに口腔機能が回復できます。
-
口腔ケア
歯ブラシやフロス、歯間ブラシを使った日常のケアが必要です。丁寧に磨きましょう。
-
食生活の見直し
野菜・果物・肉・魚など栄養バランスを考えて食べ、硬い食べ物や粘り気のある食べ物も食べるようにして噛む練習もするようにしてください。
それでは!
あなたの歯がずっと健康でいられますように。
PS.
若いうちから定期検診を取り入れケアをしっかりしていれば歯を含む口腔の健康を維持できる可能性があります。しかし、これまで検診や治療に取り組んでいなくても遅いことはありません。自覚症状がなくても検診を積極的に行いましょう。
「定期検診の予約をしたい」と思ったら、ご予約のお電話をどうぞ。電話に出たスタッフに「定期検診の予約をしたい」などのようにお伝えいただき、来院日時を決めましょう!
↓ご予約電話番号はコチラ
03-5985-4183