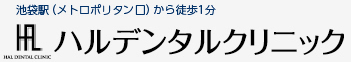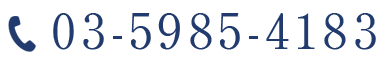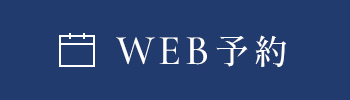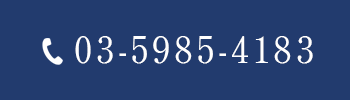意外と知らない「歯は○○より硬い」
こんにちは、春山です。
今回は、歯に関する豆知識です。ぜひ、歯のことをもっと知って大事にしてください。
それでははじめます。
歯の硬度はどれくらい?
「歯は人体の中でもっとも硬い」と聞いたことがある人も多いでしょう。
しかし、どれくらい硬いかについては知らない人の方が多いかもしれません。
モース硬度で測定した歯の硬度は下記のとおりです。
・エナメル質:6~7(水晶と同程度)
・象牙質:5~6(燐灰石と同程度)
・セメント質:4~5(骨・鉄と同程度)
鉄の硬度が4骨の硬度が5なので、セメント質がほぼ同じくらいの硬度。エナメル質と象牙質は鉄や骨より硬いことがわかります。
参考
https://www.lion-dent-health.or.jp/labo/article/knowledge/01-1/
-
エナメル質は酸に弱い
ただし、エナメル質にも弱点があります。虫歯菌のひとつミュータンス菌からできる酸です。
歯垢のバイオフィルムやプラーク中にいるミュータンス菌からできた酸がエナメル質を溶かします。予防するためには、歯みがきによるプラークコントロールとバイオフィルムの除去が大切です。
虫歯の再治療~限界は?
歯の再治療をするとき「被せ物とかやり直せば」と思っている人もいるでしょう。しかし、再治療の回数にも限度があります。虫歯の部分を削るたびに残せる部分がなくなることが大きな理由です。
-
治療の流れ
虫歯になると、その状態により下記のような治療をします。
1.コンポジットレジン(プラスチック)
2.インレー(詰め物)
3.根管治療とクラウン(被せ物)
4.再度の根管治療とクラウン(被せ物)
5.抜歯して義歯(ブリッジなど)
根管治療は神経を取り除くため歯がもろくなり、根本から割れやすくなります。できれば、小さい段階で治療を済ませたいところですね。
虫歯になりやすい人、なりにくい人の違い
生活のリズムは整ったでしょうか。不規則な生活習慣は歯・口の状態に影響を及ぼします。不規則になっている方は、早めに戻せるように対策しましょう。
虫歯の三大要素
虫歯の原因となる要素は以下の3つがあります。
- 細菌(ミュータンス菌など)
- 糖質
- 歯の質
これらの要素が積み重なって時間をかけて虫歯が進行します。すぐに虫歯になるわけではないので、できるだけ早いうちに見つけて処置することが大切です。
虫歯になりやすい人となりにくい人
-
ミュータンス菌の多少
ミュータンス菌はほとんどの人の口内にある細菌です。多い人もいれば、ほとんど持ってない人もいます。虫歯になりやすい人は、この細菌が活発に活動。なりにくい人はこの細菌が少ないと言えるでしょう。虫歯菌は1歳半から2歳半の間に入りやすいので、その時期の生活習慣には気をつけてください。
-
唾液の分泌量
唾液の作用のひとつに歯を溶かす酸を中和する作用があります。唾液の分泌量が少ないと、この働きが弱くなり、虫歯を誘発しやすいので注意してください。その他、唾液がサラサラしているかネバネバしているかも重要な要素です。ネバネバしていると虫歯になりやすいので気をつけてください。
-
歯質の強さ
エナメル質や象牙質が丈夫であれば、酸や細菌に攻撃されにくい傾向にあります。しかし、乳歯や生えたばかりの永久歯は歯質が弱いので注意が必要です。その他、先天的に歯質が弱い人も虫歯になりやすいので気をつけてください。
-
歯並び
歯並びがいいと歯みがきもしやすく、食べかすも溜まりにくいので清潔なお口の環境を維持しやすいでしょう。歯並びが悪いと反対に歯みがきがしにくくなり、食べかすも溜まりやすいため虫歯になる確率も高まります。歯並びが悪い人は、矯正治療も含めて検討してみてください。
補足
歯を守る習慣として取り入れたい習慣があります。
・フッ素の有効活用
・デンタルフロスの有効活用
・歯間ブラシの有効活用
・歯科の定期検診
フッ素の有効活用は各種論文などでも虫歯予防に効果が期待できると言われています。
デンタルフロスと歯間ブラシは歯と歯の間や歯ぐきとの境目など磨きにくい場所を磨くのに不可欠なアイテムです。最後に歯科の定期検診は歯・口の異常を早期発見するためにも4ヶ月を目安に受診しましょう。ケア用品についても承っているので遠慮なく相談してください。
虫歯になりやすい飲食物リスト
歯みがきなどのセルフケアと同じくらい大切な食習慣。
虫歯にならないためにあまり食べないほうがいい飲食物について見ていきます。
エナメル質が溶けるサイン
歯の表面にあるエナメル質は、虫歯菌が作る酸で簡単に溶けてしまいます。
その目安は大人でpH5.5以下、子どもであれば5.7以下。
※中性:pH7
食後は誰でも酸性に傾くうえ、歯の表面にいる細菌が糖を使って酸を作ります。そのため、食後すぐに歯みがきをして汚れを取って唾液の作用で中性に戻すことが必要です。
避けたほうがいい飲食物とは?
- 糖分が多い飲食物が虫歯になる原因のひとつに糖分があります。
・歯につきやすいお菓子
その中で危険なのが、粘着性のあるキャラメルやキャンディなどの食べ物です。これらは歯につきやすく、虫歯菌の栄養源になります。
・酸性の飲食物
ソーダ飲料
スポーツドリンク
柑橘類などが該当します。
いずれもエナメル質を溶かしやすく歯がもろくなるので、食べ過ぎには注意してください。特にスポーツドリンクは、角砂糖で7~10個分の糖分が入っています。
・コーヒー、紅茶
着色や汚れの原因になる他、口が乾きやすくなるので注意が必要です。
・アルコール類
コーヒーと同じく口が乾きやすくなります。
そのため、唾液の減少や虫歯・歯周病につながります。
中には糖分や酸が含まれるものもあるので気をつけてください。
・硬すぎるもの
硬すぎる食べ物は、歯の損傷につながります。また、歯に圧力がかかるため、歯周病のリスクもあるでしょう。
【選ぶ際の注意点】
・食事のバランス
ビタミンやミネラルを多く含む食事を中心に歯に負担のかかりにくい食事を心がけましょう
・歯みがき
食後の歯みがきが大切です。特に糖分や酸を多く取った場合はできるだけ早く歯磨きしてください。
・水分摂取
アルコール・コーヒーなどを飲んだあとは特に水分補給を意識しましょう。
それでは!
あなたの歯が
ずっと健康でいられますように。
PS.
歯を守るためには食事を含む生活習慣の改善や歯みがきが大切です。それと同時に歯科検診を定期的に受けるようにしましょう。違和感があってもなくても正しい歯みがきを身につけるためにも検診を受けてみてください。
「定期検診・治療の予約をしたい」
と思ったら、ご予約のお電話をどうぞ。
電話に出たスタッフに「定期検診・治療の予約をしたい」などのようにお伝えいただき、来院日時を決めましょう!
↓ご予約電話番号はコチラ
03-5985-4183